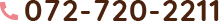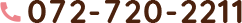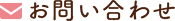ペットと同行避難をしたとしても、避難所にペットが入れるかどうかは、避難所それぞれの取り決めによって異なります。もし入れたとしても、他の避難者に迷惑をかけないようにするには、普段から適正な飼育を行っている必要があります。
多頭飼育の場合、災害時に避難所へ連れていけないので、在宅避難となることがあります。また繁殖期には脱走しようとする癖もあるため、去勢・避妊手術も検討しましょう。
愛用しているペットフード、処方されているお薬などは常備しておきましょう。持病がある場合、健康を維持する要となります。
法律で接種が義務付けられている狂犬病予防注射を始め、各種ワクチンは接種しておきましょう。フィラリア予防、ノミ・マダニ予防も重要です。
ワンちゃんやネコちゃんが離れ離れになったときのため、犬の登録・鑑札、迷子札の装着・マイクロチップなどは必ず行っておきましょう。一緒に写真撮影をしておくのも個体の識別には有効です。
ワンちゃんやネコちゃんと避難所に避難すると、他のペットと長く一緒に滞在することになります。その際にストレスをできるだけ感じないよう、日頃からケージの中で過ごす訓練をしたり、他の動物と接したりするトレーニングをしておきましょう。
当たり前のことですが、適度な運動・糞尿の始末・リードをつけての散歩など日頃から適切に行うようにしましょう。
避難所では、ペットを共同で見守ったり、自宅のペットの様子を見に行ってもらったりと、多くの方々と協力する必要が出てきます。飼い主様同士で協力できるよう、日頃から信頼関係を築いておきましょう。避難所で見知らぬ方を信頼するのは大変危険です。
避難所生活が長期化すると、場合によってはペットを飼育できないケースも考えられます。そのような状況を考えて、知り合いや親戚などと事前に話し合いを行い、もしもの時の預け先を確保することが重要です。